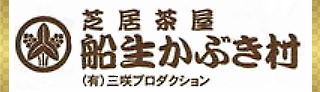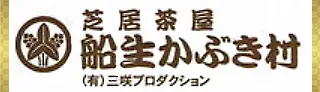観劇の意味を正しく理解し舞台芸術をより深く楽しむための知識ガイド
2025/10/05
観劇という言葉、本当の意味をご存じでしょうか?舞台芸術の世界に親しむ中で、「観劇」と「鑑賞」の違いや、その言葉が持つ豊かな文化的背景に戸惑った経験はありませんか。観劇は単なる演劇鑑賞にとどまらず、ミュージカルや歌舞伎、さまざまな舞台表現を深く味わい、劇場での体験をより豊かにするキーワードです。本記事では、観劇の意味を正しく理解し、舞台芸術の本質や関連用語、マナー、楽しみ方まで幅広く解説します。舞台芸術を味わう歓びが何倍にも広がる知識と気付きが得られることでしょう。
目次
観劇の本当の意味を知る第一歩
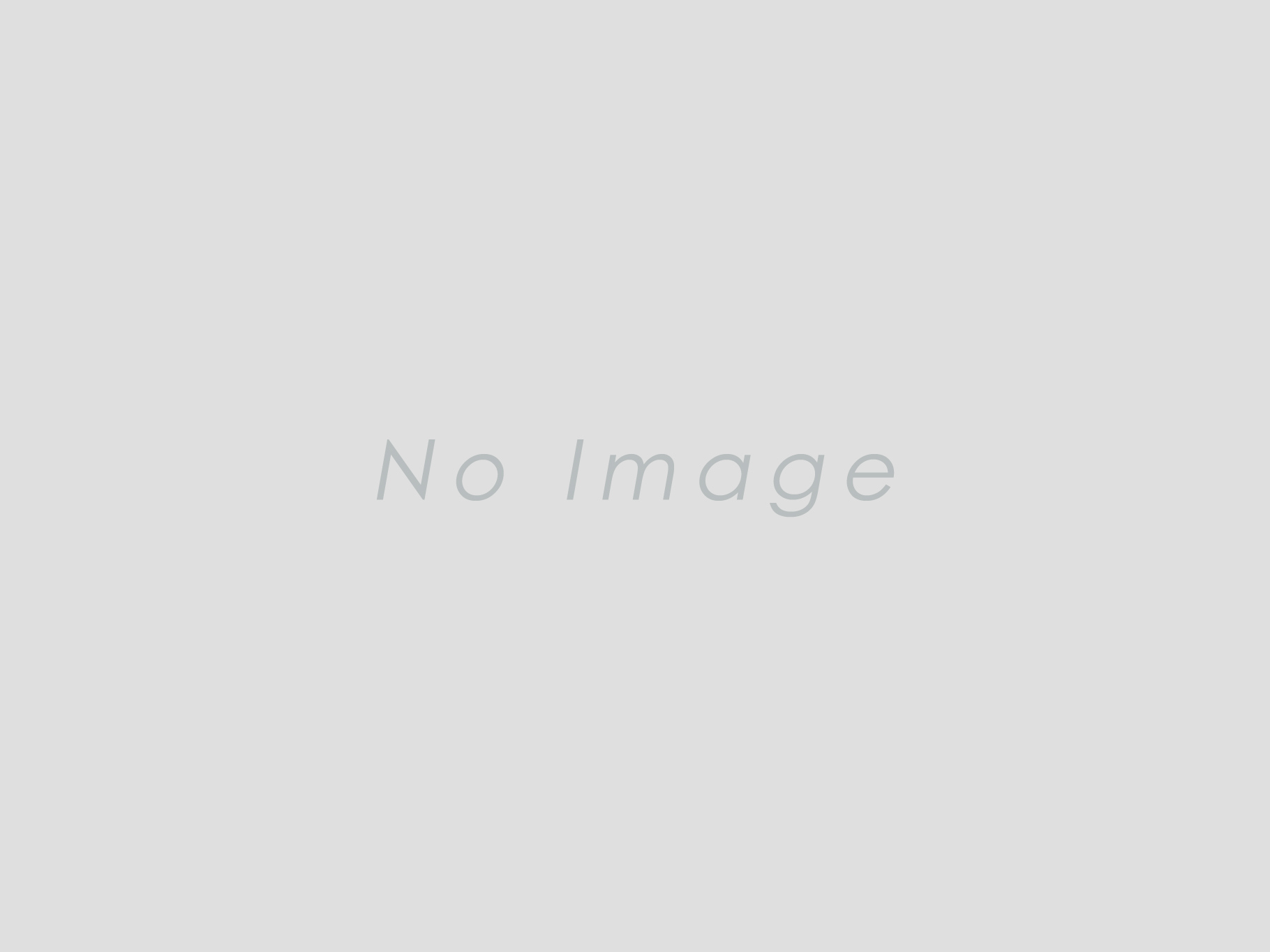
観劇の意味を正しく理解する重要性
観劇の意味を正確に把握することは、舞台芸術を深く楽しむ第一歩です。なぜなら、「観劇」は単なる演劇鑑賞だけでなく、ミュージカルや歌舞伎など幅広い舞台表現の体験を含むからです。例えば、観劇を単なる“見る”行為と捉えるのではなく、舞台全体の表現や演者の息遣い、空間の雰囲気を感じ取ることが重要です。正しい理解が、舞台芸術をより豊かに味わう土台となります。
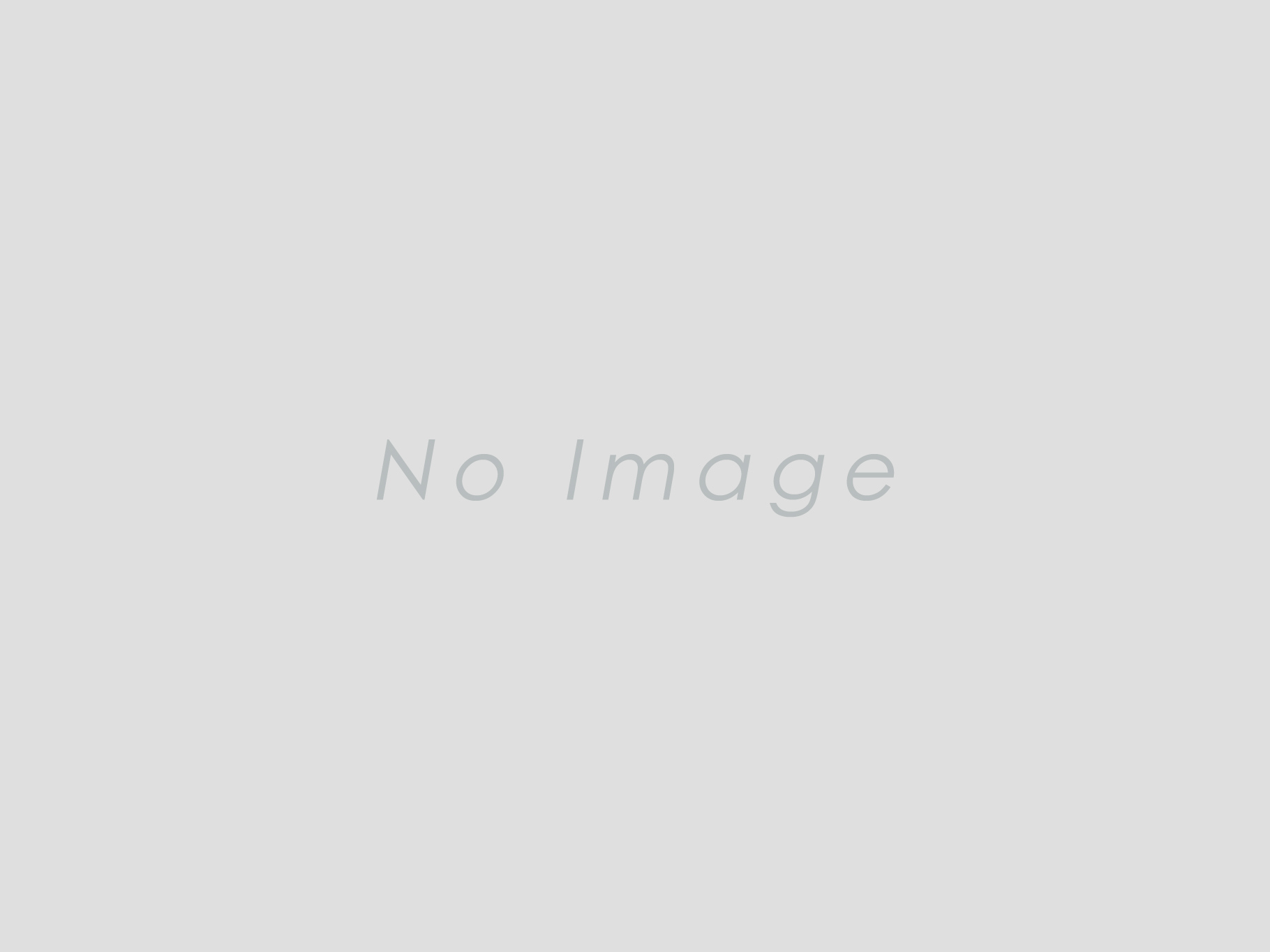
観劇が舞台芸術にもたらす価値とは
観劇は舞台芸術に独自の価値をもたらします。その理由は、観客が直接舞台を体感することで、表現者と一体となる特別な空間が生まれるためです。例えば、役者の細かな演技や生の音楽、舞台装置の工夫など、現場でしか得られない感動があります。これにより、作品への理解や共感が深まり、舞台芸術の本質を体験できます。観劇は、舞台芸術の価値を最大限に引き出す行為です。
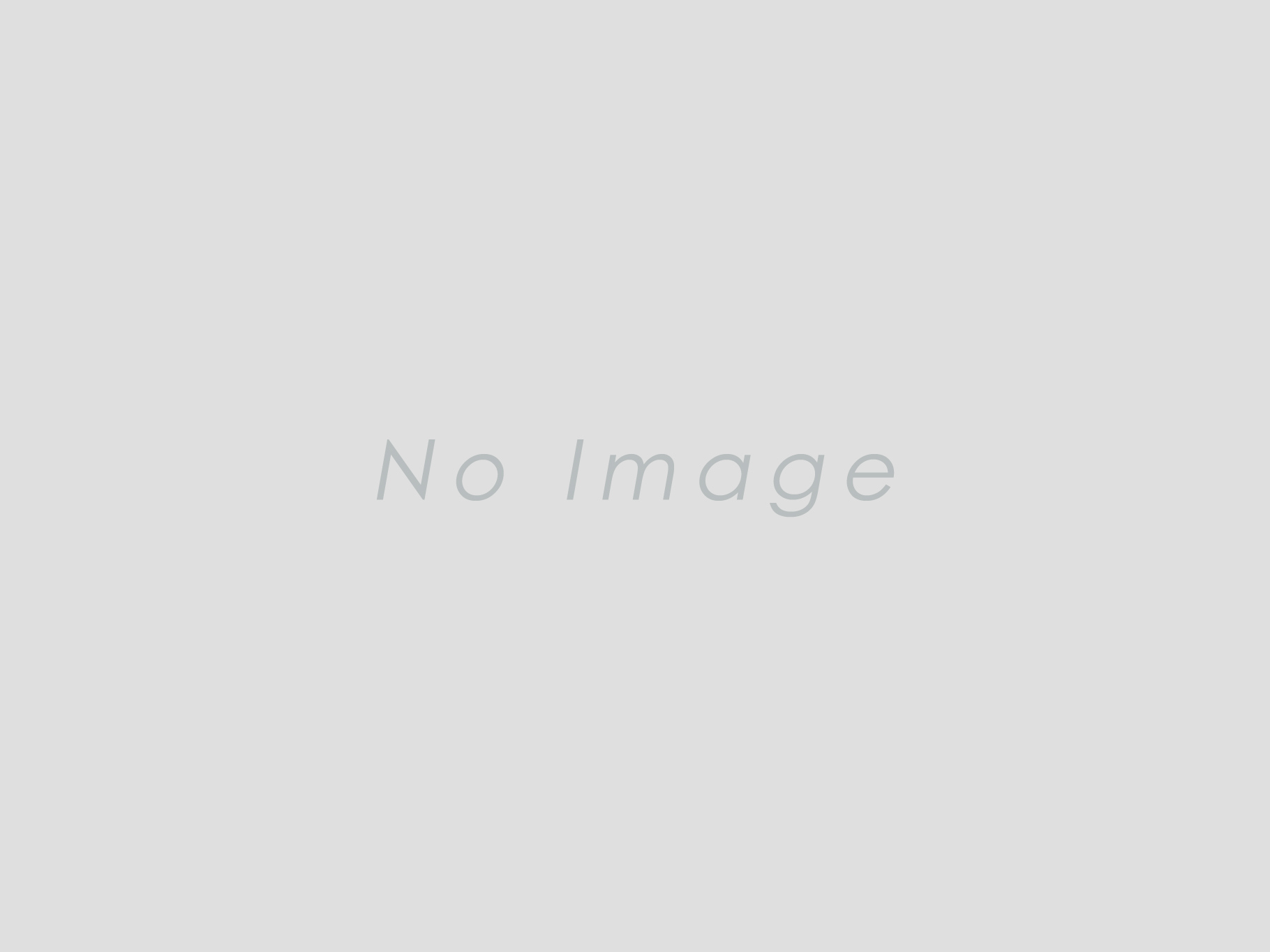
観劇と言葉の使い方と文化的背景
観劇という言葉は、演劇やミュージカル、歌舞伎などの舞台作品を「観る」行為を指します。日本では、観劇と鑑賞が使い分けられ、観劇は舞台芸術に特化した表現です。例えば、映画や美術展は「鑑賞」とされることが多いですが、劇場での体験には「観劇」が適しています。この言葉は、長い歴史や文化的背景を持ち、多様な芸術表現を楽しむ日本の文化に根差しています。
舞台芸術で味わう観劇の世界とは
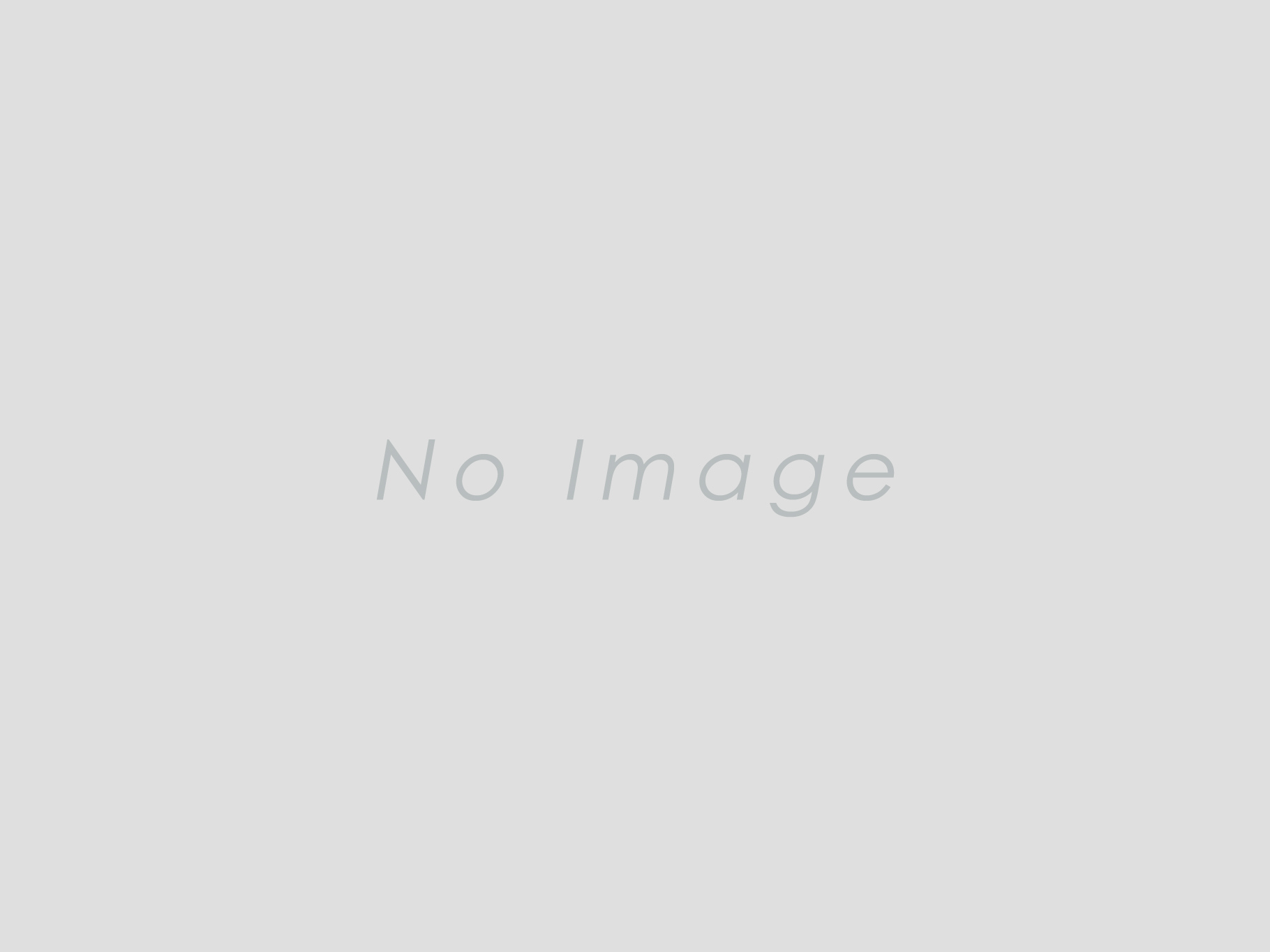
観劇が舞台芸術にもたらす感動体験
観劇は舞台芸術の本質を体感する特別な体験です。なぜなら、役者や演出家のエネルギーが観客に直接伝わり、感情の高まりや一体感を生むからです。例えば、舞台上の生演奏や迫力ある演技を目の当たりにすると、物語への没入感が格段に高まります。観劇は、単なる鑑賞を超えて、心を動かすライブ体験を提供します。
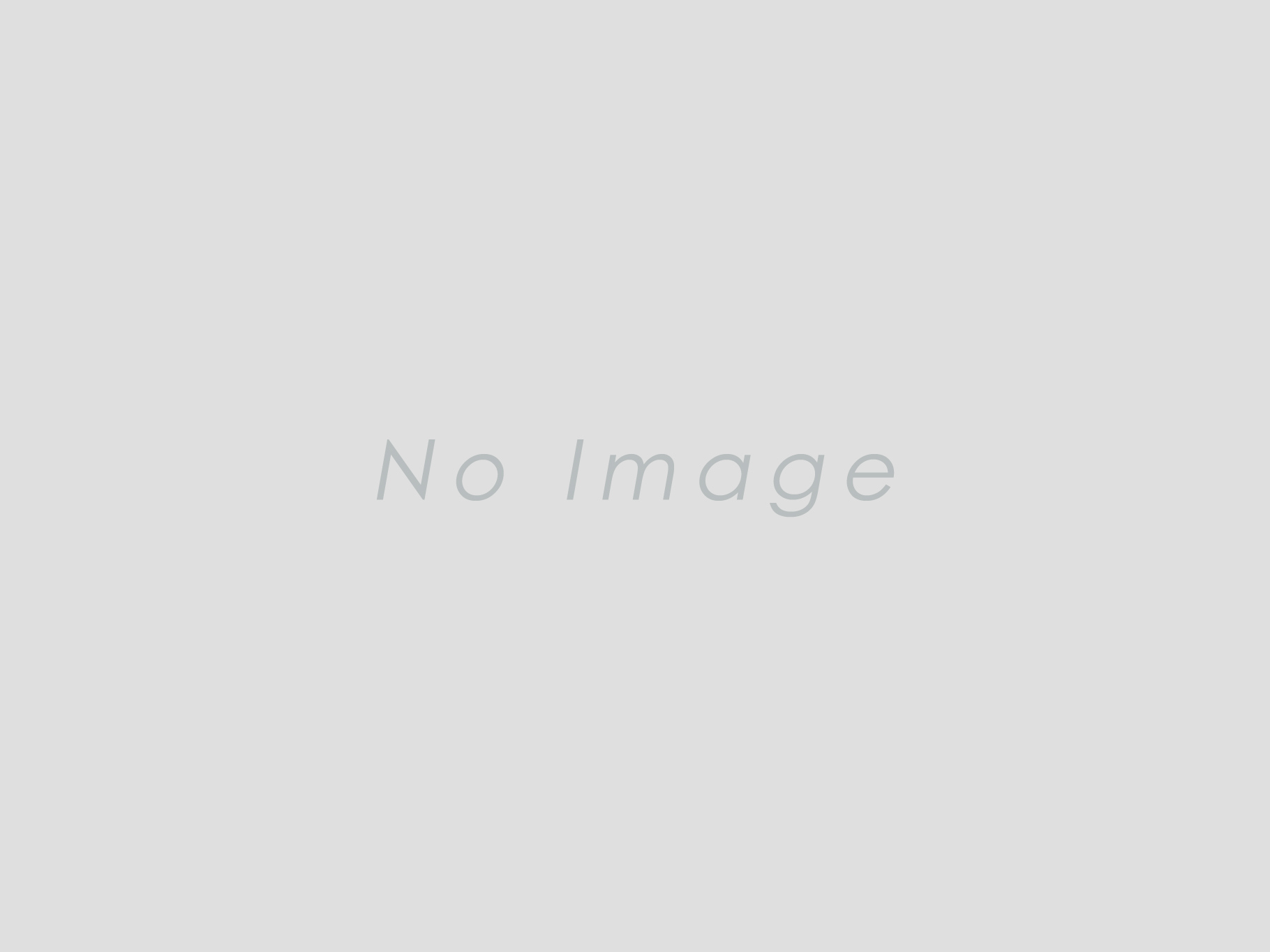
観劇の世界に広がる多彩なジャンル
観劇には演劇、ミュージカル、歌舞伎など多様なジャンルが存在します。これは、さまざまな舞台芸術が人々の価値観や興味に応えるためです。例えば、現代劇は日常の感情を描き、ミュージカルは歌やダンスで物語を表現します。ジャンルを知ることで、自分に合った観劇スタイルを見つけられます。
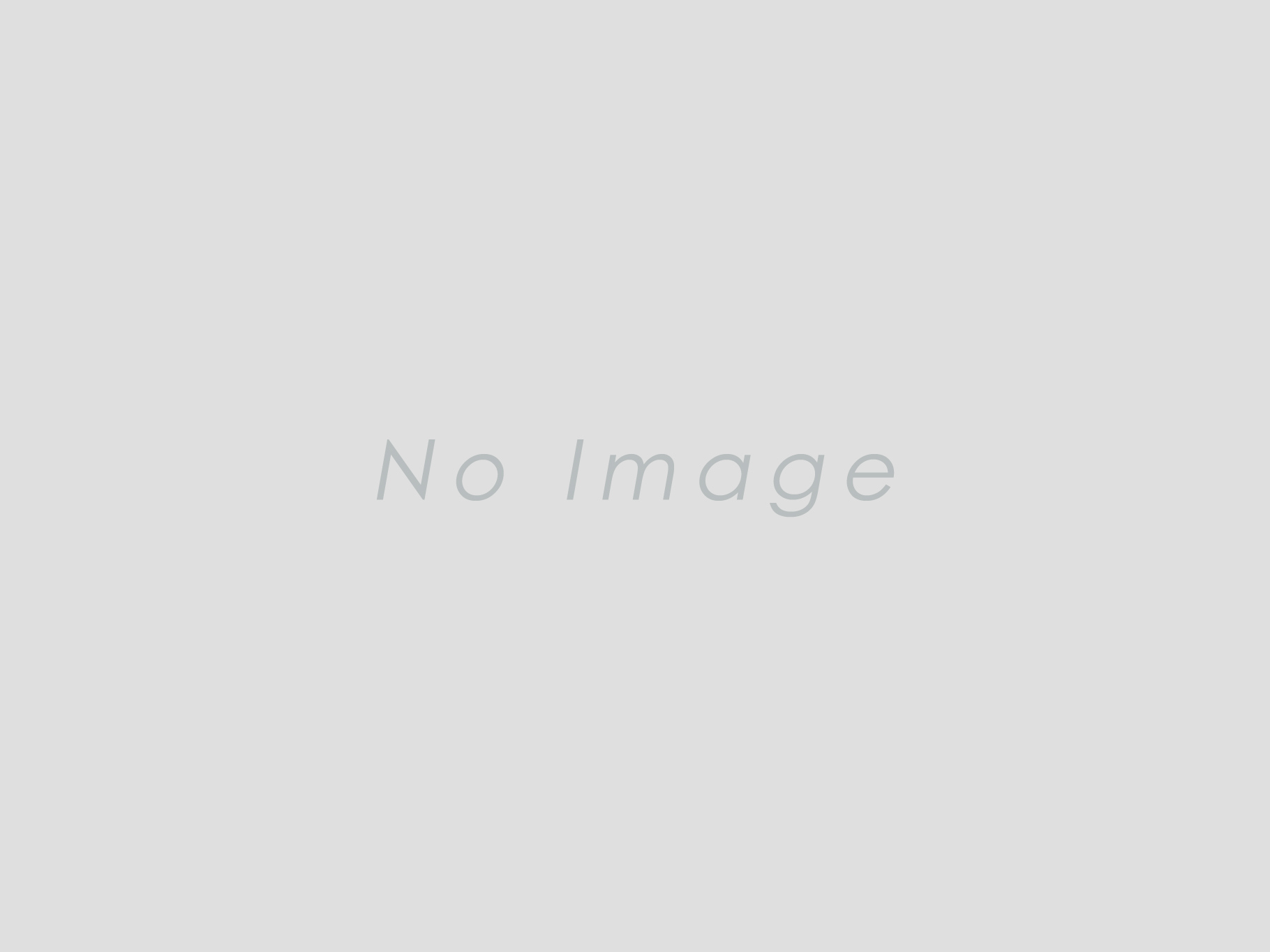
観劇で楽しむ演劇と舞台美術の魅力
観劇の魅力は、演劇の奥深い演技と舞台美術の美しさが融合する点にあります。なぜなら、役者の表情や動き、舞台セットや照明が一体となることで、物語の世界観が立体的に浮かび上がるからです。例えば、細部までこだわった美術や衣装は、観客の想像力を刺激します。観劇では視覚と感情の両面で舞台を楽しめます。
観劇と鑑賞の違いを正しく理解する
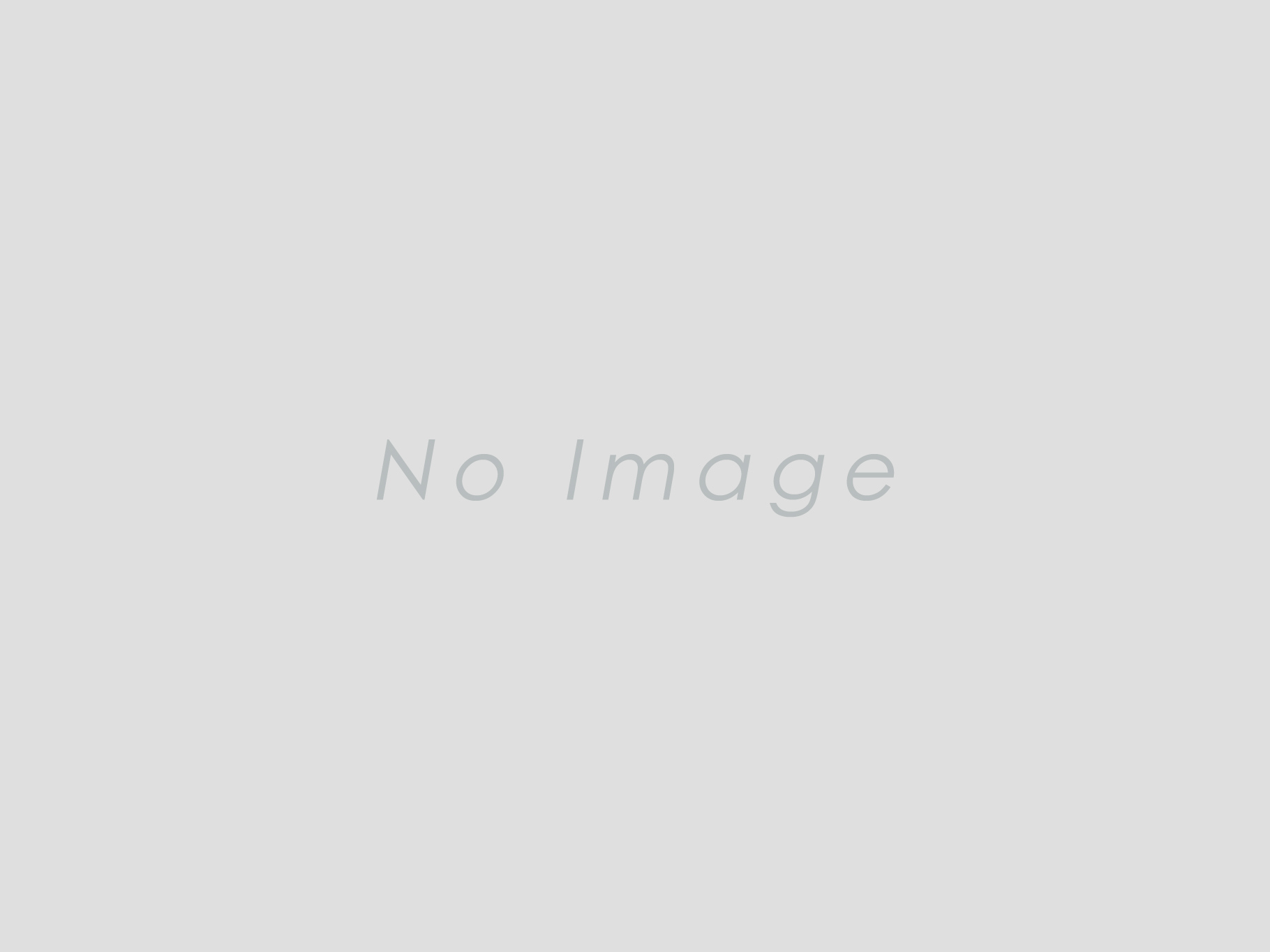
観劇と鑑賞の違いを明確に解説
観劇と鑑賞は、言葉として似ていますが、意味に明確な違いがあります。観劇は舞台上で演じられる演劇やミュージカル、歌舞伎などを実際に劇場で体験することを指します。一方、鑑賞は美術や音楽など幅広い芸術を静かに味わい、評価する行為を意味します。例えば、観劇はライブ感や臨場感を重視し、役者の表情や動きを体感することが特徴です。この違いを理解することで、場面ごとに適切な言葉を使い分けられます。
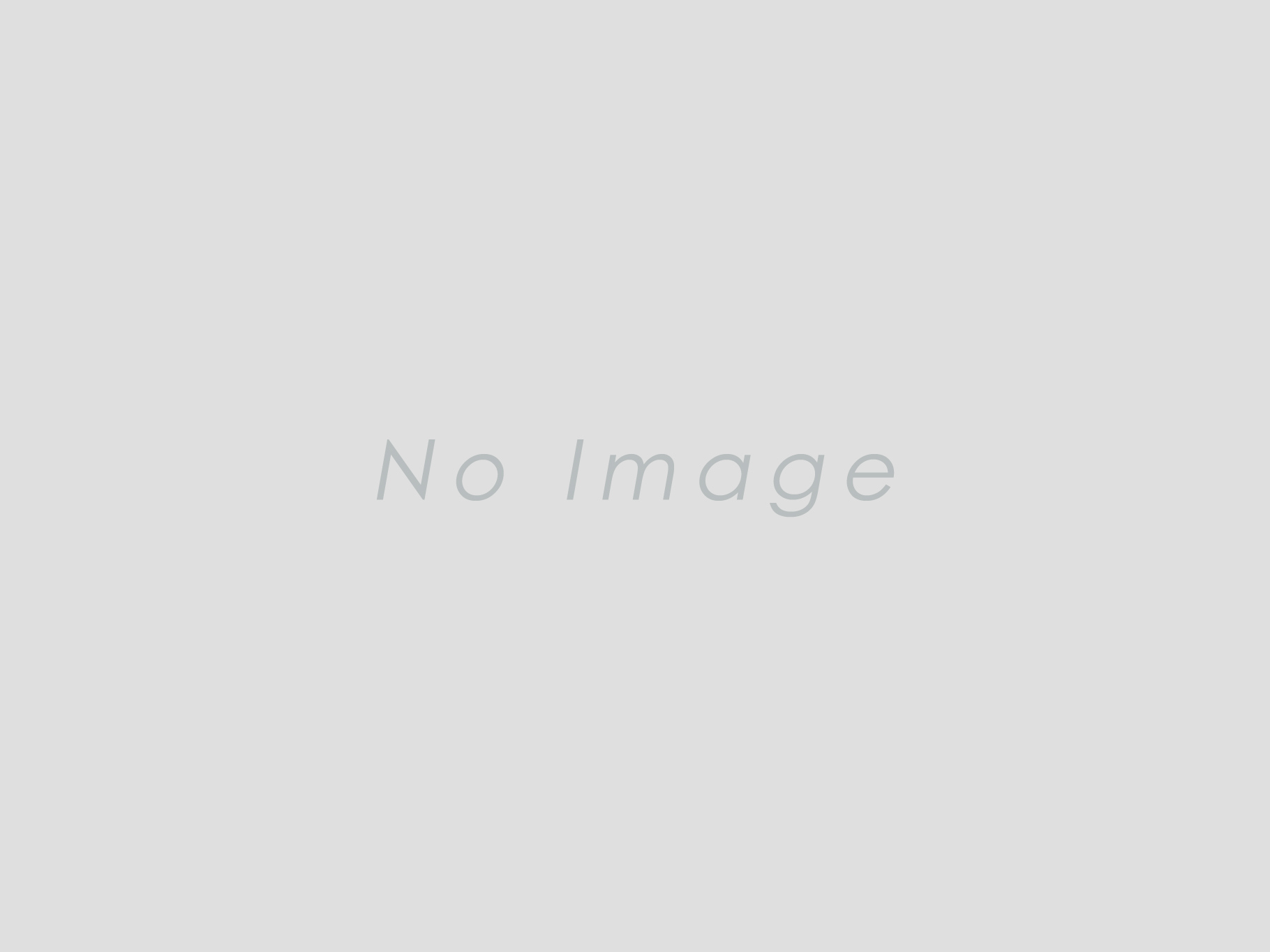
観劇と鑑賞の意味を意識した使い分け
観劇と鑑賞を正しく使い分けるには、それぞれの意味を意識することが重要です。観劇は「舞台芸術のライブ体験」に特化し、鑑賞は「多様な芸術作品を味わう」広い意味を持ちます。例えば、演劇やミュージカルを劇場で楽しむ場合は観劇、美術展や映画を静かに楽しむ場合は鑑賞と表現します。このように使い分けることで、相手に自分の体験や意図をより正確に伝えることができます。
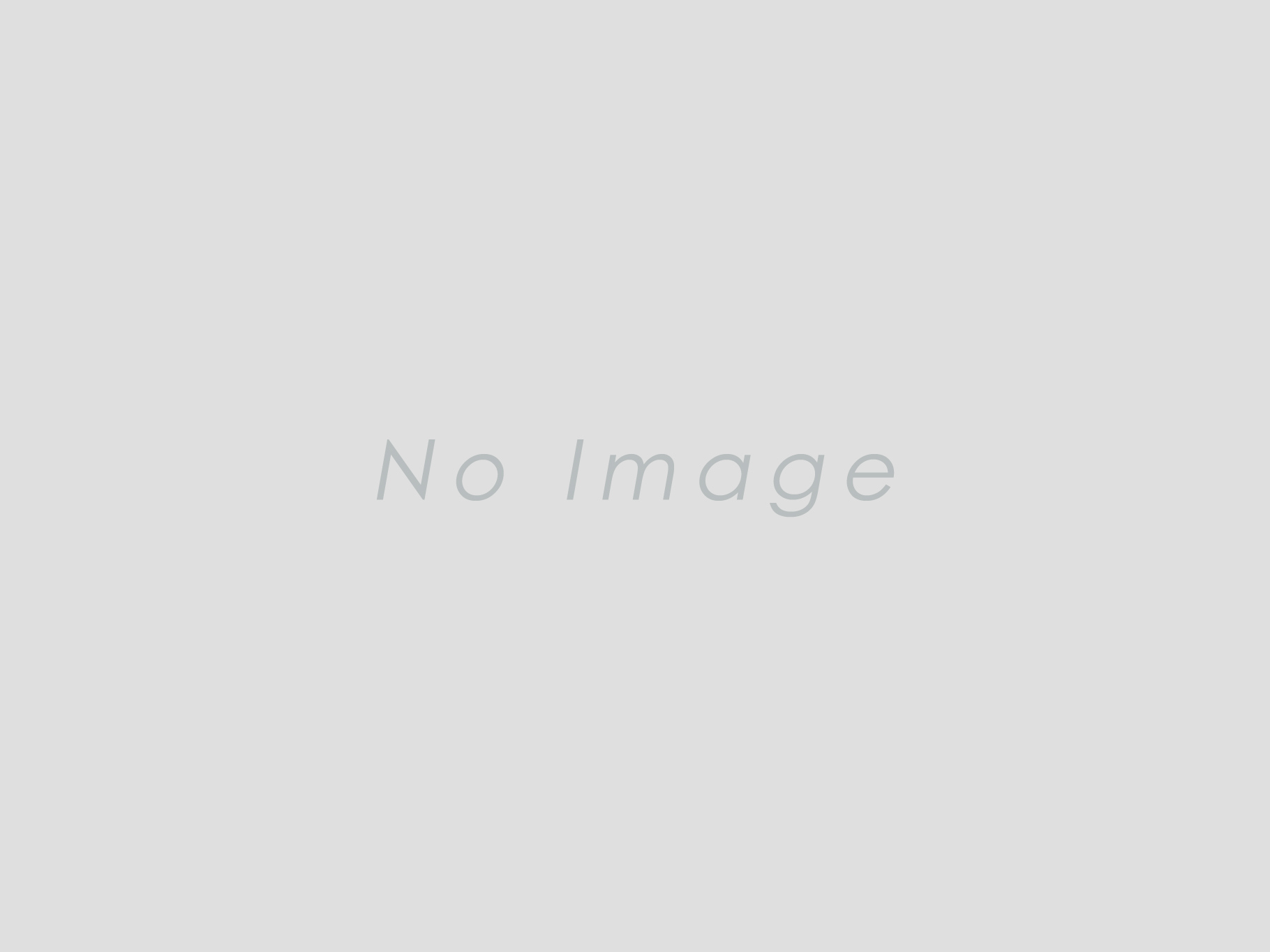
観劇と鑑賞の違いを知り言葉を正しく使う
観劇と鑑賞の違いを知ることで、言葉の使い方がより正確になります。観劇はライブ性や舞台の臨場感を重視し、鑑賞は作品全般を対象とします。例えば、友人と舞台を観た後の感想を共有する際、「観劇した」と表現することで、その場の空気や感動をより具体的に伝えられます。正しい言葉を選ぶことは、舞台芸術を深く楽しむ第一歩です。
ミュージカル観劇の魅力を深掘り
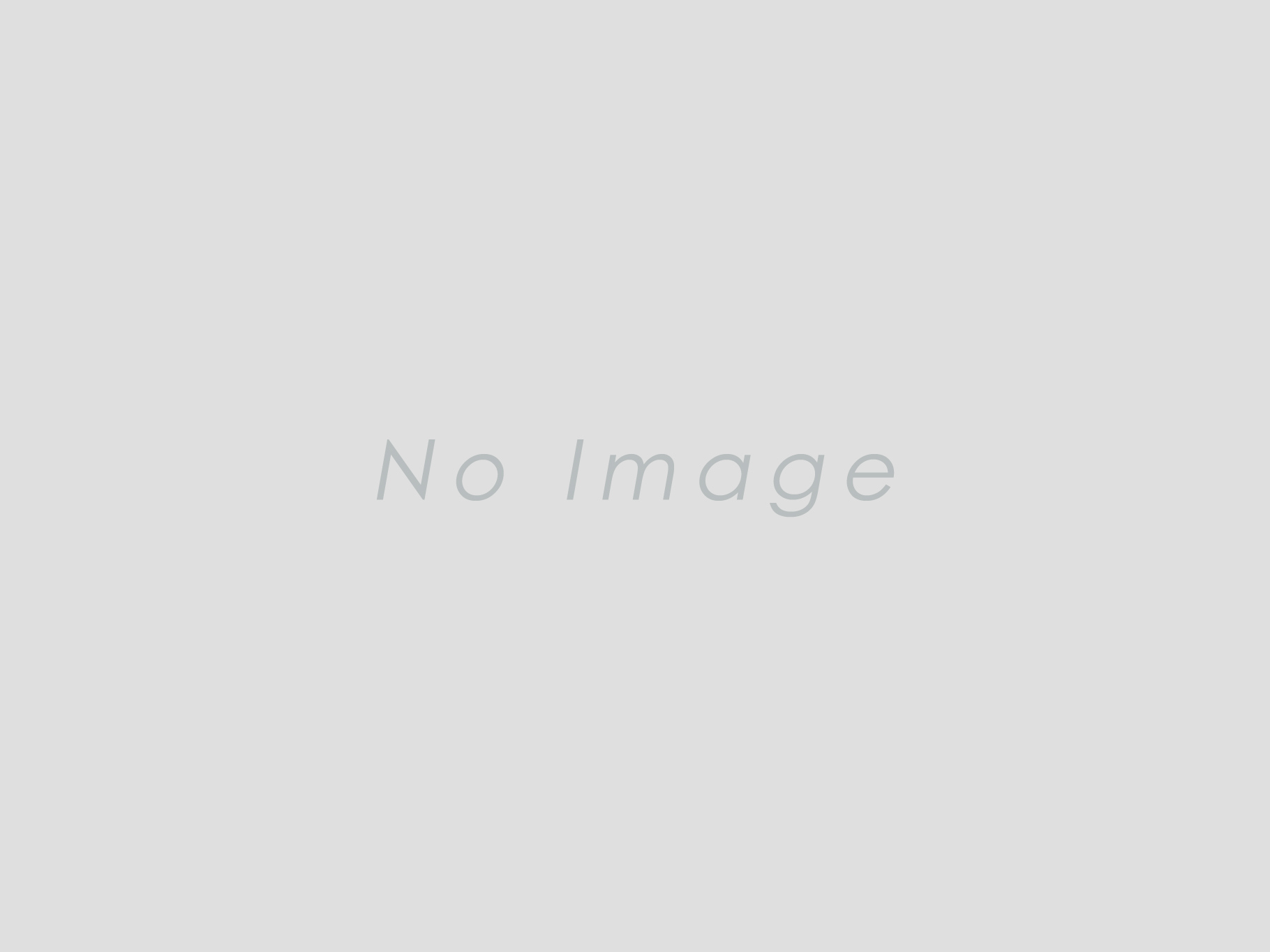
ミュージカル観劇で味わう音楽の迫力
ミュージカル観劇では、生演奏による音楽の迫力が最大の魅力です。舞台上の俳優が歌い上げるナンバーやオーケストラの生音は、劇場ならではの臨場感を生み出します。例えば、物語のクライマックスで響く合唱や、ダンスナンバーのリズムは観劇体験を一層印象的なものにします。観劇は音楽と演技が一体となった舞台芸術を、身体全体で味わえる貴重な機会です。
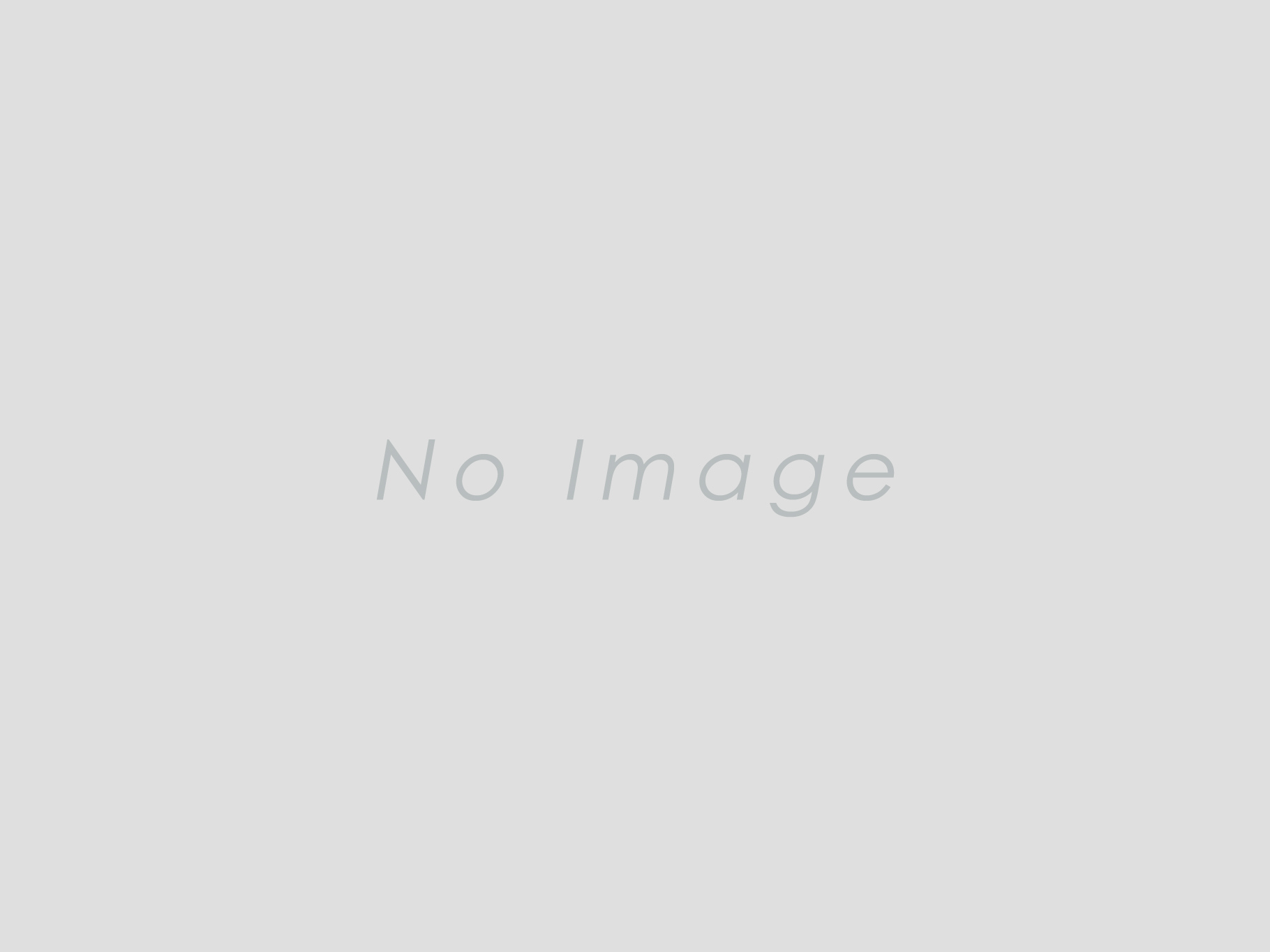
観劇がミュージカルの楽しみ方を広げる
観劇を通じて、ミュージカルの楽しみ方は大きく広がります。単に物語を追うだけでなく、演者の表情や動き、舞台装置の工夫など細部まで注目することで、舞台芸術全体への理解が深まります。具体的には、繰り返し観劇を行うことで新たな発見が生まれ、舞台ごとの個性や演出の違いも楽しめます。観劇はミュージカルの多彩な魅力を引き出す、重要なアプローチです。
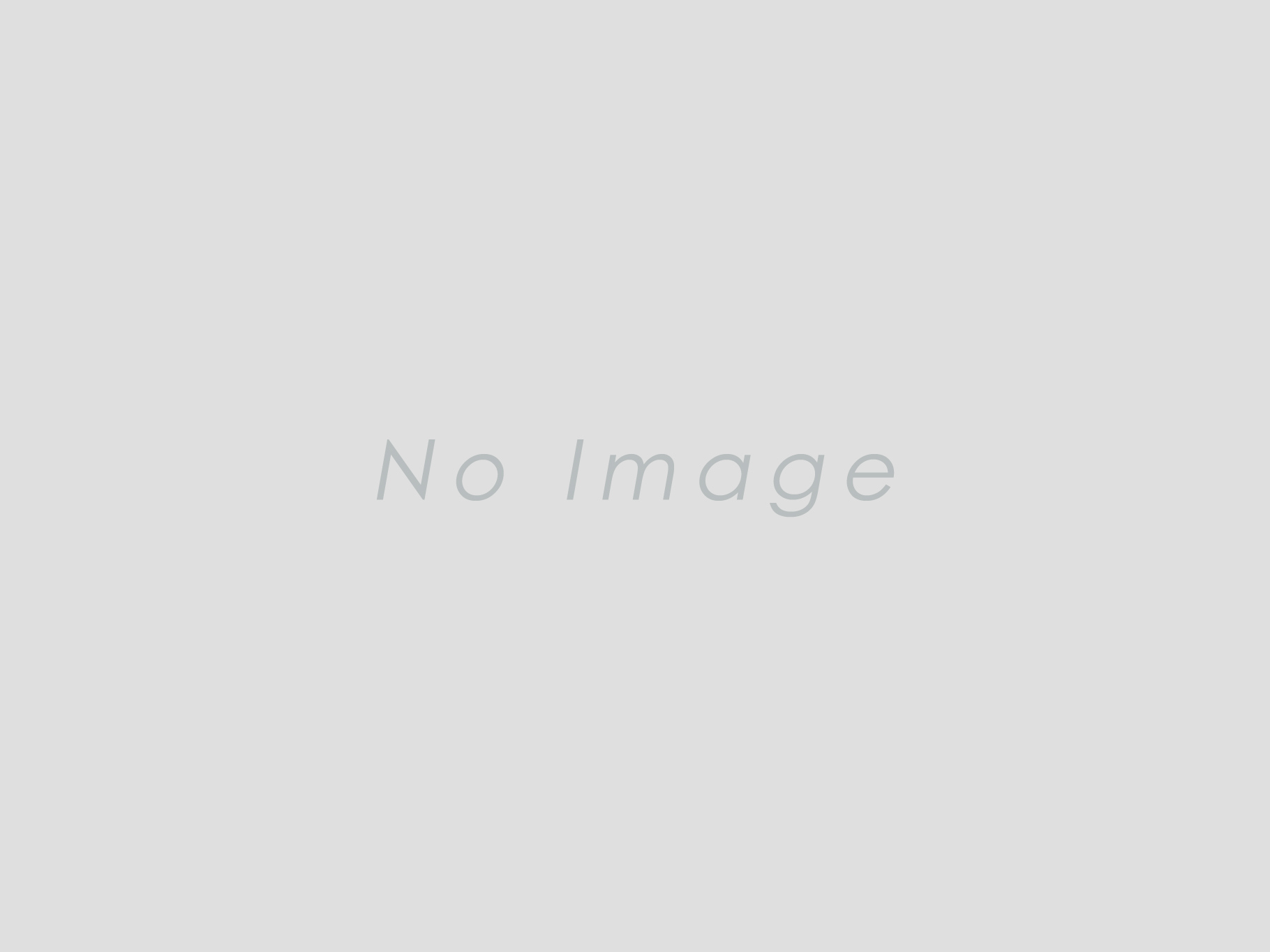
観劇を通じたミュージカルの新たな魅力
観劇はミュージカルの新たな魅力を発見するきっかけとなります。目の前で繰り広げられるライブパフォーマンスは、観る者に一体感と感動をもたらします。例えば、アドリブや日替わりの演出、キャストの個性が際立つ瞬間など、劇場でしか味わえない出来事が多くあります。観劇を重ねることで、舞台芸術の奥深さや多様性に気付き、より深く楽しめるようになるでしょう。
歌舞伎や映画でも活きる観劇の楽しみ方
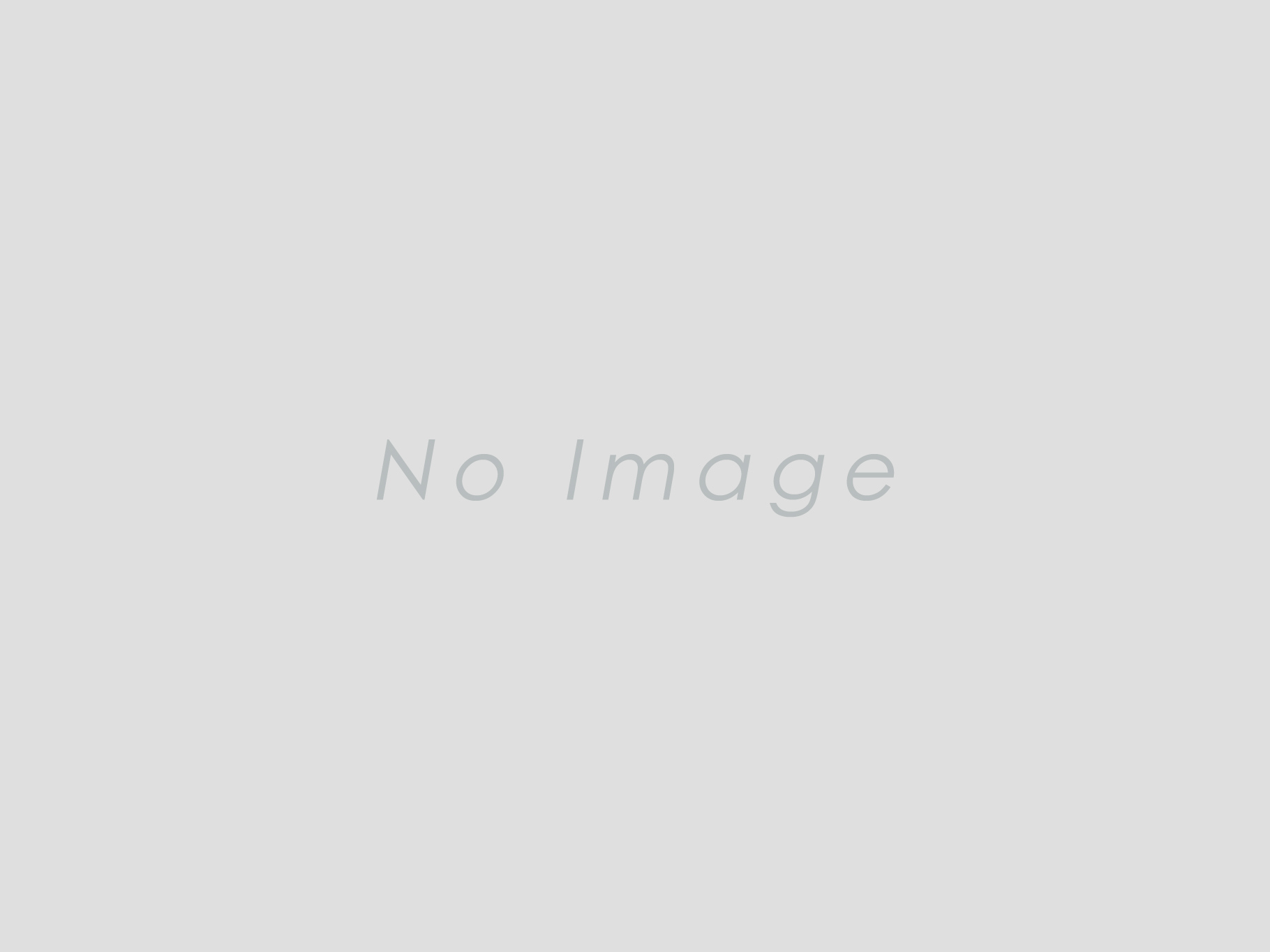
観劇の意味は歌舞伎や映画にも応用可能
観劇とは、演劇や舞台芸術を劇場などで直接体験することを指します。その意味は歌舞伎や映画にも応用でき、広義にはミュージカルやオペラ、現代演劇など多様な舞台作品の鑑賞も含まれます。観劇は単なる視聴ではなく、舞台上の生きた表現や臨場感を味わう行為です。具体的には、出演者の細やかな演技や舞台装置の工夫、音響や照明の演出などを現場で感じ取ることが観劇の醍醐味です。観劇の意味を正しく理解することで、歌舞伎や映画といった異なる分野でも舞台芸術の本質を深く味わえるようになります。
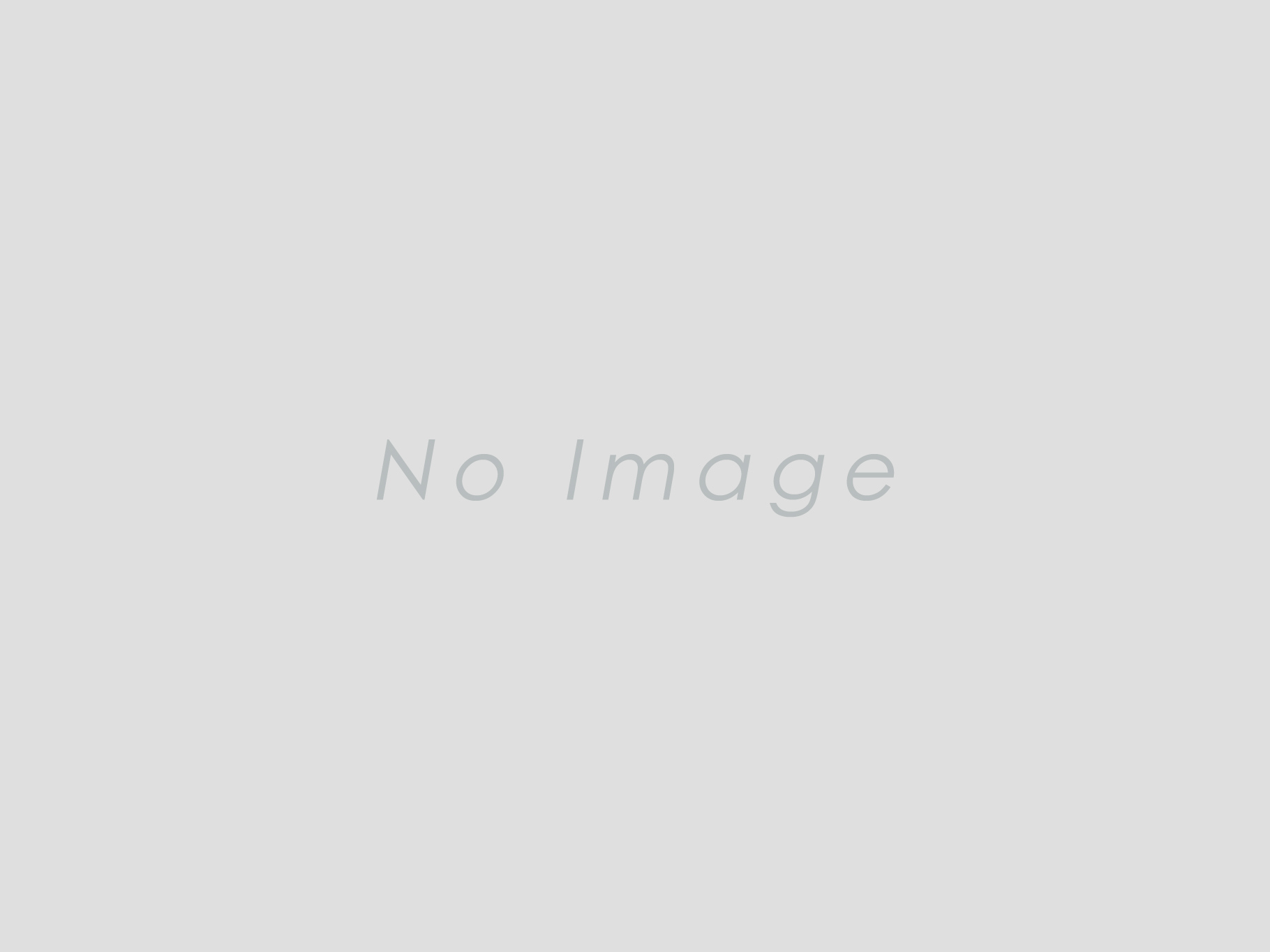
歌舞伎観劇で感じる伝統芸能の奥深さ
歌舞伎観劇は、日本の伝統芸能を肌で感じる絶好の機会です。歌舞伎独自の演出や衣装、独特な台詞回しは、他の舞台芸術にはない奥深さを持っています。たとえば、見得や隈取などの所作や化粧は、歴史と文化を色濃く反映しています。観劇の際は、演目ごとの物語背景や役者の演技に注目することで、より深い理解と感動が得られます。伝統芸能の本質に触れながら、観劇の意味と価値を実感できるのが歌舞伎観劇の魅力です。
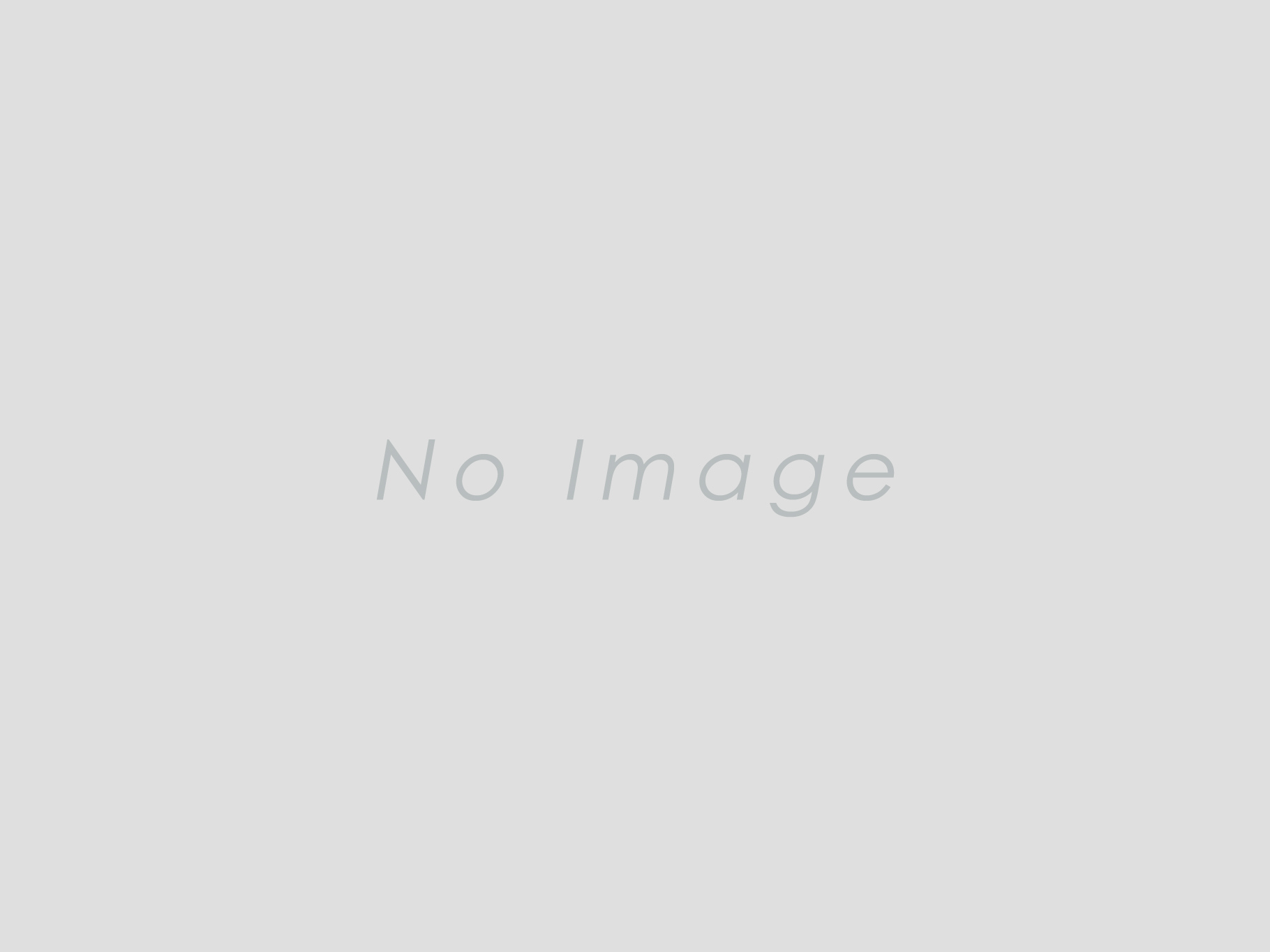
映画観劇で見つける舞台体験の新発見
映画館での観劇もまた、独自の舞台体験を提供します。大画面と音響に包まれながら、俳優の細やかな表情や臨場感ある演出を味わえるのが特徴です。映画観劇では、ストーリーの展開や映像美、音楽との一体感など、舞台とは異なる魅力を発見できます。具体的には、カット割りや編集技法を意識しながら観ることで、作品理解が深まります。映画もまた観劇の一形態として、舞台芸術の新しい楽しみ方を広げてくれる存在です。
観劇する際に押さえたいマナーと心得
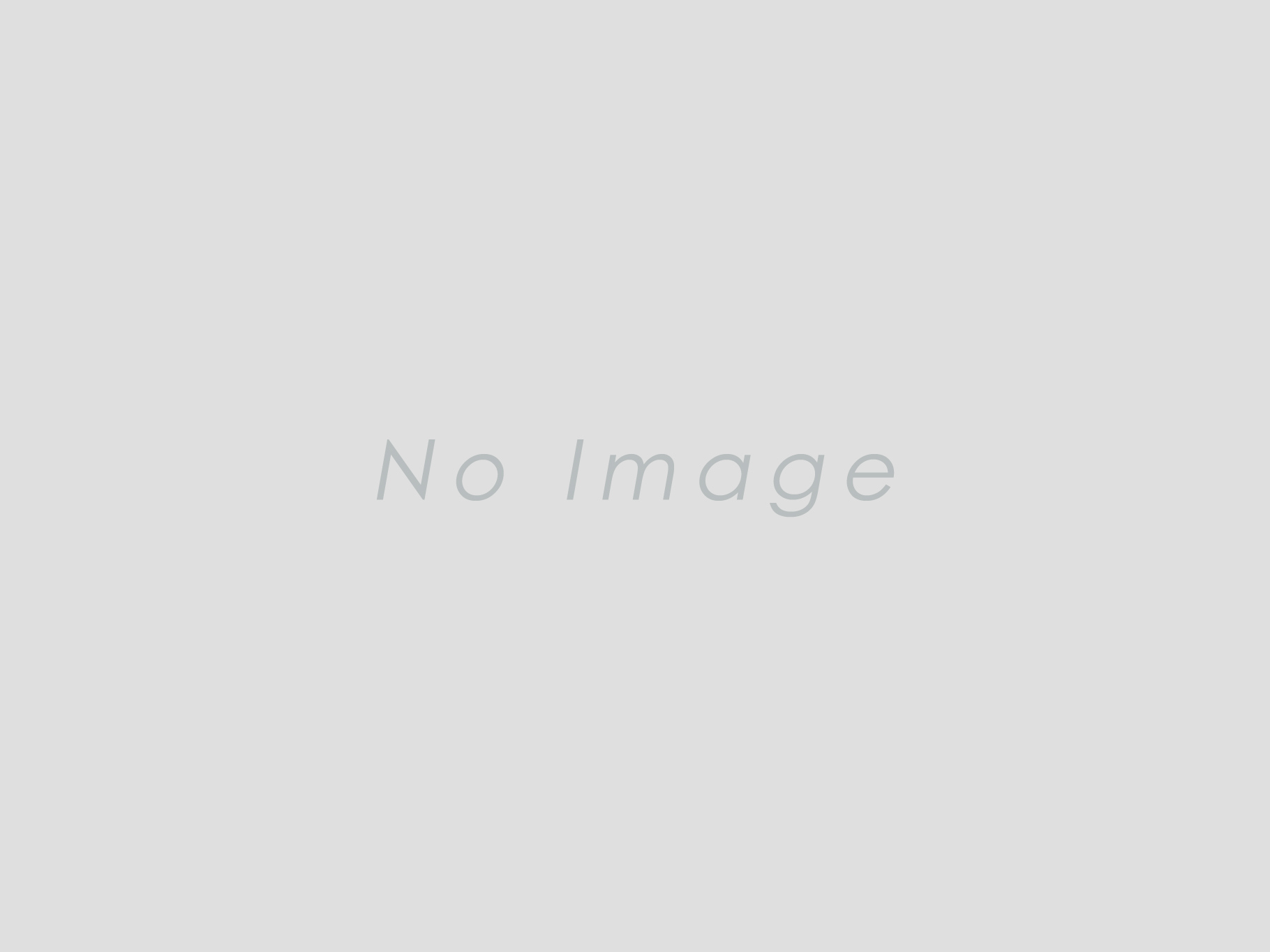
観劇の意味を理解したマナーの基本
観劇とは、舞台芸術を実際に劇場で鑑賞し、その空間や演者の表現を五感で味わう体験です。観劇の意味を正しく知ることで、単なる演劇鑑賞と異なる深い文化的背景や楽しみ方が見えてきます。具体的には、舞台と観客が一体となるライブ感や、演者の息遣いを感じる臨場感が特徴です。観劇を楽しむ際には、その意味を理解した上で、周囲への配慮や劇場のルールを守ることが大切です。これにより、舞台芸術の本質により近づくことができ、豊かな体験を得られます。
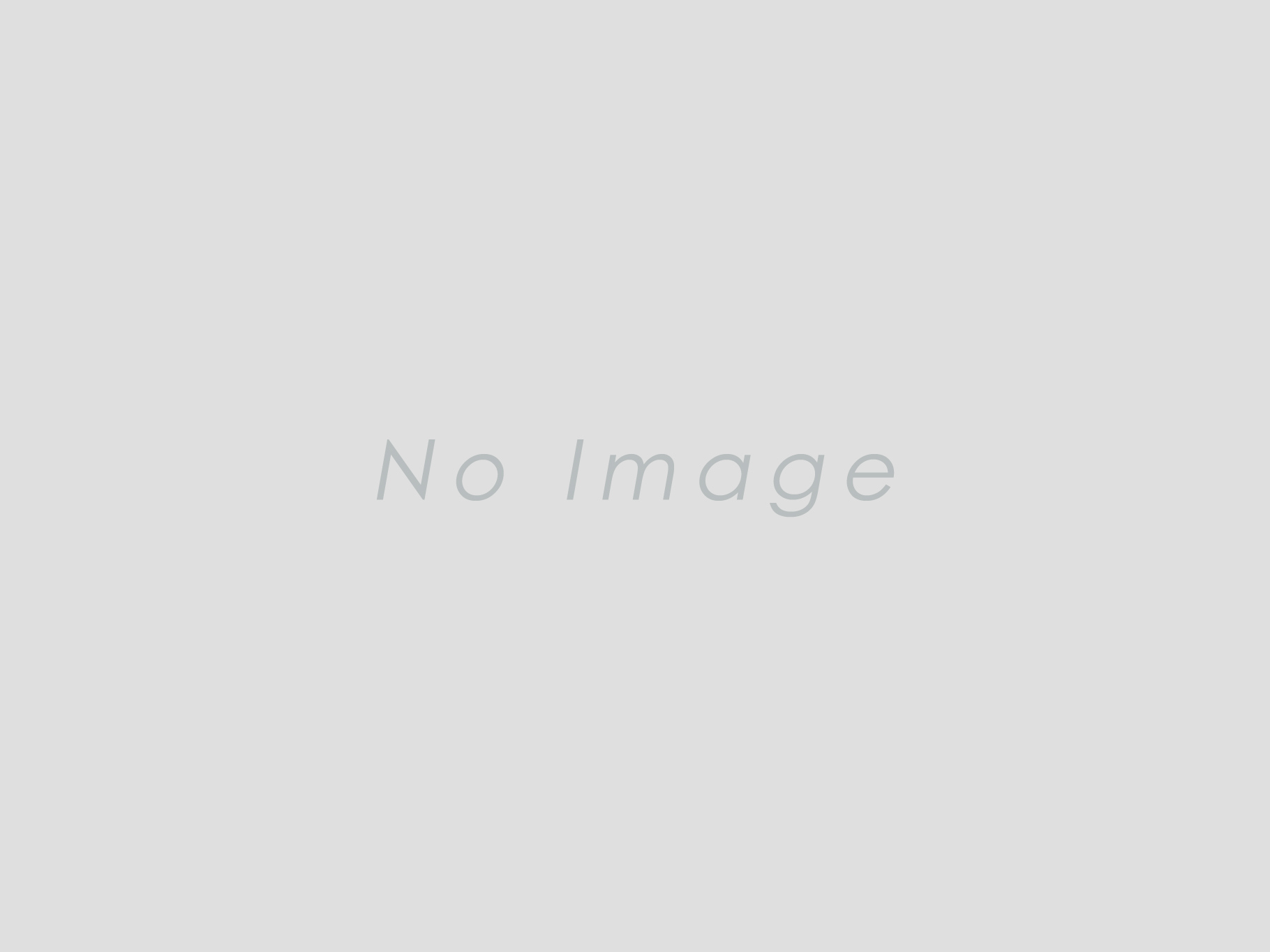
観劇時に注意したい行動と心構え
観劇時の行動は、他の観客や舞台上の演者に配慮したものが求められます。理由は、劇場という空間が共有されているため、個々の行動が全体の雰囲気や体験の質に大きく影響するからです。例えば、上演中の私語や携帯電話の使用は厳禁ですし、座席の移動も控えましょう。また、演目や劇場ごとに独自のルールがある場合もあるため、事前に確認することが重要です。こうした行動や心構えを意識することで、観劇本来の魅力と感動を味わえます。
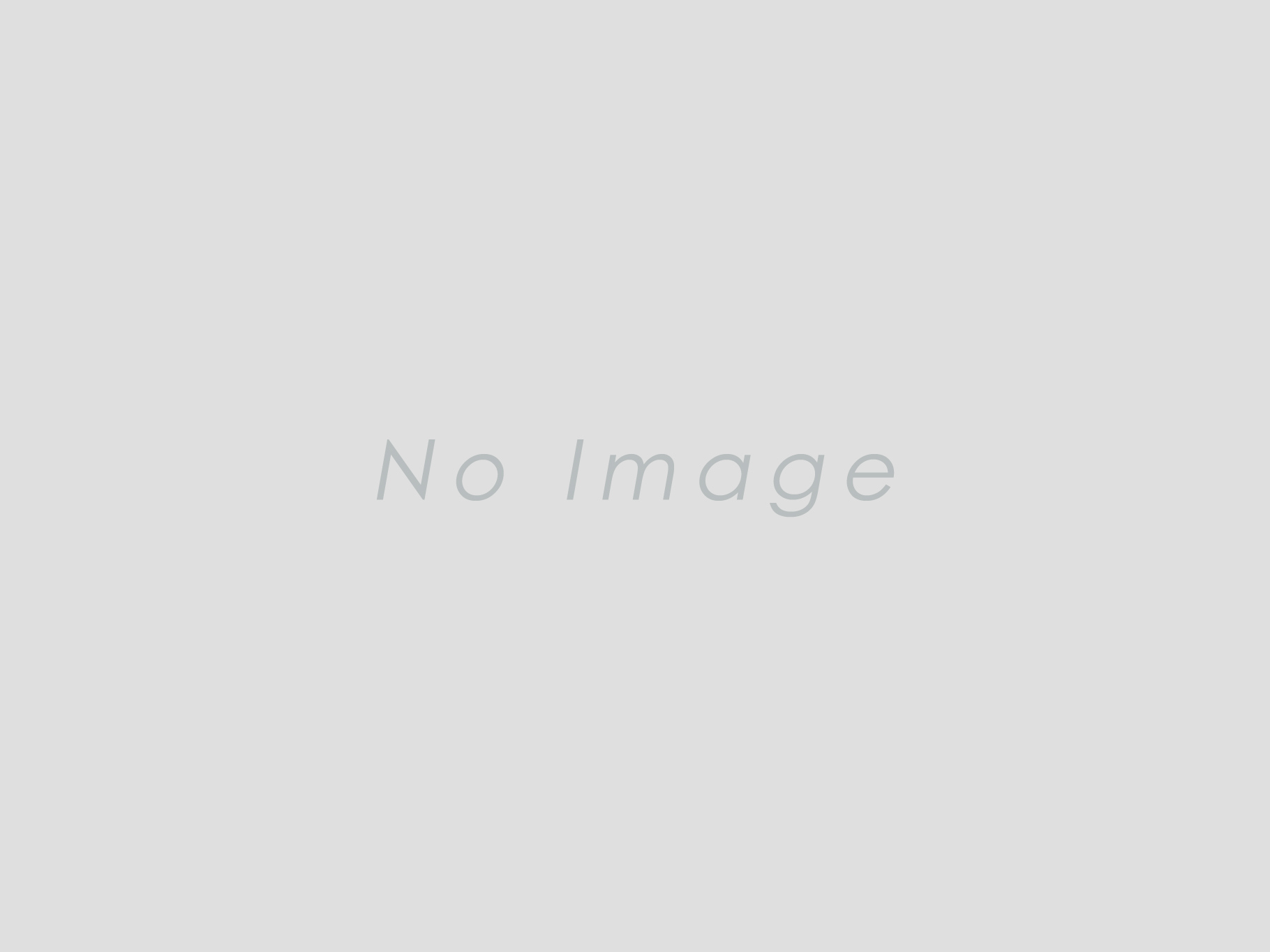
観劇を快適に楽しむためのマナー集
観劇を快適に楽しむためには、具体的なマナーを守ることが欠かせません。代表的なマナーとしては、•開演前に着席する•香水や音の出る持ち物は控える•飲食は所定の場所で行う、などが挙げられます。また、終演後の拍手や、周囲への挨拶も大切なエチケットです。これらのマナーを意識することで、誰もが心地よく舞台を楽しめる環境が整います。観劇の意味を理解し、実践的なマナーを身につけることで、舞台芸術の感動が何倍にも広がるでしょう。